![]()
![]()
 |
五藤家屋敷 五藤吉兵衛の死後、弟:為重が家督を継いで家老 として、高知城のすぐ南に広大な屋敷を構えて いました。 吉兵衛:ドラマでは、武田鉄也が演じており、一豊より 歳上で一番の家臣として多くの戦いに従軍しました。 史実は、一豊より8歳年下で、朝倉攻めで一豊が朝倉 の武将:三段崎勘右衛門の矢を顔に受けたとき一豊 の顔を踏みつけ矢を抜いた。その時の、矢とぞうりが 家宝として伝わっています。1583(天正11)年、 亀山城攻撃で一番乗りを果たすが討ち死。享年31歳 |
 |
筆山(高知城、鏡川を南に越えたところにあります) 昔から山全体が墓所として使われていた。 土佐藩主山内家ゆかりの寺や墓所がこの山の 周辺にあります。 15代豊信(容堂)以外の藩主の墓がこの山の 中にあります。 |
 |
真如寺
(筆山の前にあります) 山内家の菩提寺 |
 |
要法寺 筆山の東側にあります。 一豊が長浜城主となった時に、愛知から住職が 呼ばれ、以来、掛川、高知と移転していく。 一豊だけでなく、弟:康豊の信仰もあつかった。 山内家の三葉柏の紋がお寺の瓦などに 刻まれている。 |
|
山内神社 |
|
 1806(文化3年)年、土佐藩10代藩主豊策(とよかず)により、 初代藩主の一豊とその夫人の見性院(千代)、2代藩主忠義(ただよし)を 祀るために高知城内に造営された藤並神社に始まる。 1935(昭和9)年4月、15代豊信(とよしげ)・16代豊範(とよのり)を祀る 「別格官幣社山内神社」が創建された。 1945(昭和20)年、戦火により両神社とも焼失し、以降、仮宮で祭祀が 行われていた。 1970(昭和45)年、社殿を再建して藤並神社を合祀し、土佐藩歴代の 全ての藩主を祀る神社となった。 |
|
 山内容堂公像 |
 資料館は、山内神社内にあって、土佐藩主 山内家の資料、美術工芸品を保存公開して います。 これらの資料は、2004(平成16)年に 全て(6万7千点)が高知県に移管されました。 |
  |
土佐円満神社 高知城内にあります。 謂れなどは不明のようです。何でも円満に いく様にとお参りされるのがいいようです。 |
 |
土佐稲荷神社(大阪)(地図) 六代藩主:豊隆(とよたか)の創建で、土佐藩の 大阪蔵屋敷の中に鎮守社として祀られていた。 明治になって、土佐士族:岩崎弥太郎の所有となり、 岩崎の事業:三菱の守り神となりました。 大阪城から西へ2kの所にあり、一豊時代の 大阪屋敷がこのあたりにあったと言われています。 現在も土佐堀通りと言う地名が残っています。 |
 八代豊敷(とよのぶ)寄進の灯篭 (名前が刻まれている) |
 稲荷内に馬の銅像がありますが、 いわれは何も書かれていません。 千代の買った馬か。 |
|
||
 道路左:山内家下屋敷 右:山内容堂公屋敷跡 容堂が藩主であった、1864(元治元)年に、この地に 山内家下屋敷を建てたときに警護の武士が宿泊する場所 として、この長屋が建てられた。 |
||
  長屋1階は、7区画に分けられ4部屋は畳敷き、その他は板敷きと 土間です。2階は3部屋に分けられています。 |
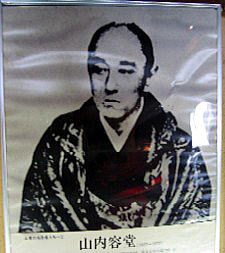 山内容堂公(下屋敷資料室) |
| 1827(文政10年)年11月27日生まれ、名は豊信(とよしげ)、 容堂は隠居してからの号。 福井藩主・松平春嶽、宇和島藩主・伊達宗城、薩摩藩主・島津斉彬とも 交流を持ち幕末の四賢侯と称された。 龍馬がたてた政権を朝廷に返す案「船中八策」を理解しており、 容堂はこれを妙案と思い、15代将軍・慶喜に建白。 1867(慶応3年1)年11月9日に、大政奉還が成立した。 東京で妾を十数人も囲い、酒と女と作詩に明け暮れる豪奢な晩年を送った。 明治5年、積年の飲酒が元で脳溢血に倒れ、1872(明治5)年7月26日、 46歳で生涯を閉じた。 |
 容堂誕生地の碑(追手門の東) 容堂誕生地の碑(追手門の東) |
 |
手嶋家屋敷 城の北側の江の口川沿いに位置し、 幕末の土佐藩中級武士の長屋門と母屋が 資料館として残っています。 手嶋家は、掛川から一豊に従って土佐入りし、 家禄250石の御馬廻り役で、上士と呼ばれ、 長宗我部の家臣:郷士より身分が高かった。 (一般公開されています) |
 古いはりまや橋 |
 現在のはりまや橋 |
南国土佐を後にして 作詩・作曲 武政英策 (昭和34年) 南国土佐を あとにして 都へ来てから 幾年ぞ 思い出します 故郷の友が 門出に歌った よさこい節を 土佐の高知の 播磨屋橋(はりまやばし)で 坊さん簪(かんざし)買うを見た |
|
高知と言えば、よさこい節で知られる「はりまや橋」です。 城下町の堀川に架けられた橋で御用商人の北岸の播磨屋宗徳の 屋敷と南岸の櫃屋道清(ひつやどうせい)の屋敷の通路として 架けられた私橋です。 朱塗りの欄干になったのは、1958(昭和33)年に映画撮影用に 塗られた。堀川は、1966(昭和41)年に埋め立てられました。 |
|